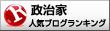7月20日の参議院選挙では自民公明の与党が大敗しました。石破茂氏が総理になって以後、衆議院、東京都議会、そして今回の参議院選挙でいずれも完膚なきまでの惨敗を喫しました。しかし石破氏は敗北の責任を取ろうとはせず、総理続投の姿勢を明らかにしました。
長く日本の政治を見てきた者からすれば、現在の政局は1980年代前後のそれに酷似しています。
選挙での大敗、そして石破氏の辞任拒否に重なるのは1979年の政局です。
当時の大平正芳総理率いる自民党は同年の衆議院選挙で敗れました。その主因は大平総理が財政改革のための増税を掲げて選挙を戦ったためでした。増税を掲げて選挙に勝った例はほとんど聞いたことがありません。
選挙の敗北を受けて、自民党の反主流派は総理の辞任を要求しましたが、総理はこれを拒否しました。当時非常に力のあった田中角栄氏の派閥(自民党内で最大の派閥)が大平総理を支えていたためです。
その結果として、自民党は歴史に名高い「40日抗争」に入ります。今でも時々テレビで、故浜田幸一議員が「こんなことをしても自民党は良くなるはずがない」と叫びながら、党内のバリゲードに使われていた椅子や机を片付けている映像が放送されますが、40日抗争時の映像です。
もう一つ似ているのは、同盟国である米国との関係悪化です。現在は関税問題や対中国姿勢(麻薬関連を含む)の問題でぎくしゃくしている印象ですが、1980年頃にも日米の同盟関係の解釈でゴタゴタがありました。
1981年、大平総理の後を継いだ鈴木善幸総理は当時のロナルド・レーガン大統領との会談の後に、日米の同盟関係には「軍事的意味合いはない」などと発言。ハト派の宏池会出身だった鈴木氏としては軍事的関係を強調したくなかったのかもしれませんが、この発言が元となって日米関係は悪化。翌年に鈴木氏は突然辞任しましたが、米国との関係悪化が大きな要因だったと言われています。
その後の展開ですが、鈴木辞任の後に総理となったのがタカ派として鳴らした中曽根康弘氏です。中曽根氏は強力に行政改革を進める傍ら、米国との関係改善に尽力。レーガン大統領と個人的にも「ロン、ヤス」とファーストネームで呼び合うほどの強い関係を築き、当時世界で覇権を急速に拡大していたソビエト連邦(現ロシア)の封じ込めに努めました。
「歴史は繰り返す」と言いますが、1980年前後のパターンが繰り返されるとすれば、今後の展開はどうなるのでしょうか。
まず想定されるのは「40日抗争」の再来とも言えるような大抗争に自民党は突入することになります。
そして次の総理になるのは、中曽根氏を彷彿とさせるような自民党内では比較的タカ派の人物。候補として考えられるのは高市早苗氏や小林鷹之氏あたりでしょうか。
特に高市氏は選挙中に「腹くくった」「党内の背骨入れ直す」と発言するなど総理の座への意欲をほのめかせています。
そして新たに総理となる人物は、トランプ米大統領と協力して中国封じ込めに尽力するということになるのかもしれません。
果たして1980年前後のパターンが繰り返されるのか否か―今後の展開に注目です