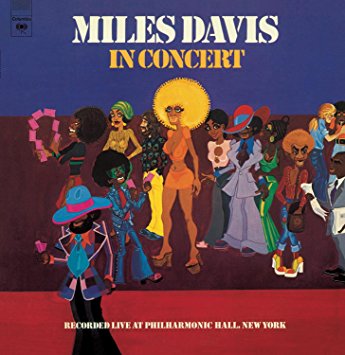
マイルス・デイビスはあまりにも多くの名盤を残しており、また音楽の質も、1950年代、60年代、70年代、80年代で大きく異なる。そのために、作品の人気投票をすると、かなり意見が割れてしまうことが多い。
このCDは1970年代前半、問題作と言われた「On the Corner」のライブ盤というべきもの。歴史的な評価を見ても、到底名盤とは言えず、マイルスファンの間でも「駄作」と決めつけるむきもある。
私自身も70年代に初めてこれを聴いた時は「どうしようもない駄作」とみて、その後、数年間は一顧だにしなかった。だから、この作品に対する厳しい評価はよくわかる。
ところが、このCDがいつのまにか自分の愛聴盤の一つになっていた。今は駄作とは思わない。せいぜい二流盤というところだろう。まず、ワウワウペダルを導入したマイルスのトランペットは悪くない。彼のソロだけ聴けば、名盤「アガルタ」「パンゲア」にもそう引けはとらない。
もうひとつの楽しみは多くのミュージシャンが参加していることもあって、音に厚みがあること。マイルスのソロのバックでも、他の8人が色々な試みをしているのが分かる。何回も聴いていると、以前には気づかなかった新たな音の発見があるのだ。
レコードの時代には、ギター、シタール、ベース、コンガ、タブラなどリズム楽器の音が無秩序に絡みあって、単なる音のカタマリ、もしくは洪水のようにしか聞こえなかった。どの楽器が、どの音を出しているのかも判別できない状況だった。
ところが比較的最近のCDでは、どの楽器がどの音を出しているかもかなり鮮明になってきた。単なる音のカタマリ、リズムの洪水ではなくなり、かなり奥深いものにも聴こえてくる。キーボードがとっているソロも聞こえてくる。
これは製作者側が音源をリミキシングしたこと、加えてオーディオ装置の性能向上によるところが大きいのだろう。
70年代のマイルスバンドの特徴としては、電気楽器の導入、リズム重視ということが一般的によく言われるが、リズムを強調するため、参加ミュージシャンが増えたことも特徴だろう。50年代、60年代のマイルスバンドは5人だったが、ここではなんと9人も入っている。
これだけの大人数をマイルスが起用したのには、大きな狙いがあったはずだ。しかし残念なことにレコード時代には、参加ミュージシャンの入魂の演奏が、単調なリズムのカタマリにしか聞こえなかった。マイルスバンドの面々に対してあまりに気の毒だ。
技術的進歩によって、音楽が生き生きと甦り、マイルスの音楽的試みがより明確に見えてきたのは喜ばしい。そしてマイルスの「Bitches Brew」からアガルタへの進化の道筋もよりはっきりしてきた。
かつて、この作品を一聴して駄作と決めつけ、見切りをつけたファンは多いだろう。ただ機会があれば、リミキシングされた比較的新しいCDを、ある程度良い音響装置で聴いてみることをお勧めする。「こいつら、リズムの裏でこんなことやってたのか!」という新たな発見、驚き、喜びがあると思う。
今後もリミキシングなどによって、再評価される作品が出てくるのではないか。そんなことを期待しながら70年代のマイルス聴き続けている昨今ではある。
- 投稿タグ
- miles davis, マイルスデイビス
